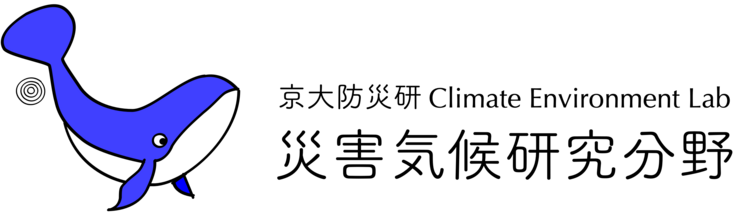中下さんと榎本教授、卒業生の石井さん(現気象庁)による論文が出版されました。
Nakashita, S., T. Enomoto, and S. Ishii, 2024: Multi-scale uncertainty of mesoscale convective systems in the Baiu frontal zone: A case study from June 2022. J. Meteor. Soc. Japan, 102 , 599-631, doi:10.2151/jmsj.2024-032.
東アジアの初夏には、ユーラシア大陸東部から日本列島上空まで伸びる数千kmの梅雨前線が、約1ヶ月に渡り断続的な雨をもたらします。この梅雨前線上では数百kmスケールの低気圧がしばしば発生し、その低気圧内では数〜数十kmスケールの対流が発達する階層的な構造が見られます。この数〜数十kmスケールの対流が集まって激しい雨風をもたらすシステムのことをメソ対流系と呼びます。このメソ対流系は局所的な地域に連続的に集中豪雨をもたらす線状降水帯の発生要因ともなるため、メソ対流系の発生・発達を正確に予測することが重要です。しかし特に九州地方に激しい雨をもたらすメソ対流系は東シナ海上で発達し、海上では観測が十分に得られないため、陸上で発達するメソ対流系と比較して東シナ海上で発達するメソ対流系の予測可能性はあまり研究されていません。
このような海上で発達するメソ対流系の発生メカニズムに対する理解を深めるため、2022年6月19日に3隻の研究船(長崎大の長崎丸、鹿児島大のかごしま丸、三重大の勢水丸)による東シナ海集中観測が実施されました(Manda et al. 2024)。この集中観測では3隻からそれぞれ1時間おきに大気の鉛直構造を測るラジオゾンデが打ち上げられ、観測期間中に2回のメソ対流系を観測しました。
本研究では、観測された2つのメソ対流系の予測可能性を、初期値を少しずつ変えた複数の予報(アンサンブル予報)によって調べました。アンサンブル予報の実施には、米国国立環境予測センター(NCEP)で用いられていた領域大気モデルMSM(Juang 2000)を利用しました。このNCEP MSMは全球モデルからのずれを計算する摂動法という手法を用いており、全球モデルが精度良く計算できる大規模な構造を保持することができるため、梅雨前線帯のような階層的な構造を持つ現象をシミュレーションするのに適しています。また、アンサンブル予報は各予報どうしが十分にばらつくことが必要ですが、このような予報をもたらす初期値を作る手法として、モデルの予測の中で発達してきた変数や位置を求める成長ベクトル法(Toth and Kalnay 1993)を用いました。この成長ベクトル法はかつてNCEPや気象庁のアンサンブル予報システムにも用いられており、計算が簡便な割に性質の良い初期値を作成できることが知られています。
アンサンブル予報の結果から、観測された2つのメソ対流系のうち、最初に観測されたメソ対流系は、アンサンブル予測によりその予測のばらつきが適切に表現されることがわかりました。このメソ対流系は水平約100kmほどの大きさの低気圧を伴っており、また大気の層は高さ5000 m近くまでよく湿っていました。アンサンブルメンバーの中で精度良くメソ対流系を予測できたメンバーは、この低気圧と非常に湿った大気の層を精度良く再現できていました。さらに、アンサンブル予測のばらつきを利用して観測を取り込むアンサンブル同化手法を用いて、3隻によるラジオゾンデの情報を同化すると、低気圧と湿った大気層の表現が修正され、このメソ対流系の予測精度が著しく改善することがわかりました(図1)。これらの結果は、最初のメソ対流系の予測の鍵が低気圧と大気の層の水蒸気分布であり、大気の擾乱と鉛直構造を捉える観測が予測精度の向上に重要であることを示しています。
一方で、後半に観測されたメソ対流系は最初のものよりも予測が困難でした。このメソ対流系は東シナ海を流れる暖かい海流(黒潮)上で、暖かい海面から蒸発する水蒸気の影響を受けて発達しており、明確な大気の擾乱を伴っていませんでした。そのため、大気にだけ摂動を与えたアンサンブル予測ではそのばらつきを捉えることが難しく、また3隻による観測も予測精度の改善にほとんど寄与しないことがわかりました。それでも比較的精度の良いメンバーでは、黒潮上での蒸発による熱エネルギーの放出が他のメンバーよりも大きく、暖かい海洋がメソ対流系の発達に影響を与えたことが示唆されました。
2つのメソ対流系の予測可能性の比較から、東シナ海上で発達するメソ対流系を精度良く予測するためには、大気だけでなく海洋の影響も適切に考慮し、双方にばらつきを与えたアンサンブル予測を行うことが重要であると考えられます。

図1 2022年6月19日0400 UTC(日本時間13時)における、アンサンブル予測による深い対流の発生率。色は全メンバーのうち、深い対流(雲頂の輝度温度が215 Kを下回る)を予測したメンバーの割合を示し、白い等値線はひまわり8号によって観測された輝度温度が215 Kの領域を示す。左が3隻の観測を同化した予測、右が同化していない予測の結果。